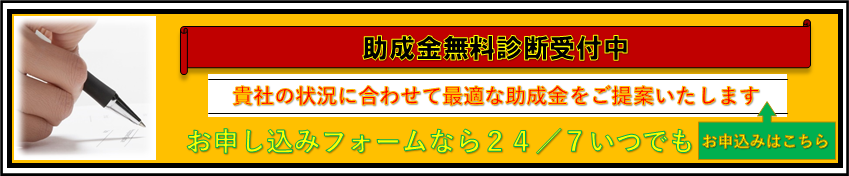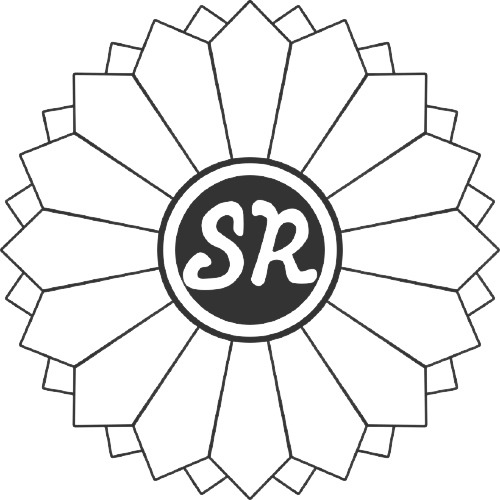
埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で外国人雇用に関する助成金のことなら
わらび南社会保険労務士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
|---|
休業日 | 日曜・祝日 |
|---|
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成するものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
この助成金の特例措置が講じられております。
申請方法や支給額なども異なりますので、詳しくは
【新型コロナ】雇用調整助成金をご覧ください。

受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
対象となる措置
雇用調整助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1および2を実施した場合に受給することができます。
1 事業活動の縮小を余儀なくされる中で、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る (以下同様))の雇用の維持を図るために、その者に対して次の(1)~(3)のいずれかの措置(以下「雇用調整」と総称する)を実施する計画を策定し、管轄の労働局またはハローワークへ事前に届け出ること
(1)休業
次の①~⑤のすべてに該当する休業をおこなうこと
① 労使間の協定によりおこなわれるものであること
② 「判定基礎期間」(※8参照)における対象労働者に係る休業または教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
③ 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
④ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑤ 次のアまたはイであること
ア 所定労働日の全1日にわたるもの
イ 当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上おこなわれるもの
(2)教育訓練
次の①~⑤のすべてに該当する教育訓練をおこなうこと
① 労使間の協定によりおこなわれるものであること
② 「判定基礎期間」(※8参照)における対象労働者に係る休業または教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
③ 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、かつ、受講者を当該受講日に業務(雇用調整助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かせないものであること
④ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑤ 次のアまたはイに該当するものであること
ア 事業所内訓練の場合
事業主が自ら実施するものであって、受講する労働者の所定労働時間の全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたりおこなわれるものであること
イ 事業所外訓練の場合
ア以外の教育訓練で、受講する労働者の所定労働時間の全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたりおこなわれるものであること
(3)出向
次の①~⑬のすべてに該当する出向をおこなうこと
① 雇用調整を目的としておこなわれるものであって、人事交流のため、経営戦略のため、業務提携のため、実習のため等におこなわれるものではなく、かつ、出向労働者を交換しあうものでないこと
② 労使間の協定によるものであること
③ 出向労働者の同意を得たものであること
④ 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること
⑤ 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
⑥ 出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認められること
⑦ 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該出向者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させていないこと
⑧ 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること
⑨ 雇用調整助成金等の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものでないこと
⑩ 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること
⑪ 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
⑫ 出向元事業所において、雇入れ助成の対象となる労働者や他の事業主から雇用調整助成金等の支給対象となる出向労働者を受け入れていないこと
⑬ 出向先事業所において、出向者の受入れに際し、自己の労働者について雇用調整助成金等の支給対象となる出向をおこなっていないこと
2 1の雇用調整を、下記「支給額」の1に示す「対象期間」中に実施すること
注意 次の場合は支給対象となりません。
1 次の(1)~(14)のいずれかに該当する教育訓練
(例示:予定している訓練が助成の対象となるかは要確認)
(1)職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としないもの
(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等)
(2)職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)
(3)趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)
(4)実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(例:講演会、研究発表会、学会 等)
(5)通常の事業活動として遂行されることが適切なもの
(例:自社の商品知識研修、QCサークル 等)
(6)当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
(例:入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT 等)
(7)法令で義務づけられているもの
(8)事業所内で実施する訓練の場合で通常の生産ラインでおこなわれるものなど、通常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産されたものを販売するもの
(9)当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識または技能を有する指導員または講師によりおこなわれないもの
(10)指導員または講師が不在のまま自習等をおこなうもの
(11)転職や再就職の準備を目的としたもの
(12)過去におこなった教育訓練を、同一の労働者に実施するもの
(13)海外で実施するもの
(14)外国人技能実習生に対して実施するもの
2 次の(1)~(4)のいずれかに該当する労働者に対する雇用調整
(1)同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
(2)解雇を予告された者、退職願を提出した者または事業主による退職勧奨に応じた者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く)
(3)日雇労働被保険者
(4)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)等の支給対象となる者
3 同一の事由により、通年雇用助成金等の支給を受けていて、当該支給事由によって助成金を申請する場合
対象となる事業主
雇用調整助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと
(1)上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇用調整をおこなった労働者(以下「支給対象者」という)の出勤、休業、教育訓練または出向の状況、および賃金、休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
(2)労働局等の実地調査に応じること
2 次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
(1)一般事業主(下記(2)~(4)以外の事業主)
(2)特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主(雇用維持等地域事業主)
(3)厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主または大型生産激減事業主)の関連事業主(下請事業主等)
(4)認定港湾運送事業主
3 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由(※1)により「事業活動の縮小」を余儀なくされたものであること。「事業活動の縮小」とは次の(1)または(2)の要件を満たす場合をいいます。
※1 「景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由」とは、景気の変動および産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化のことをいうので、次の①~③に掲げる理由により事業活動を停止または縮小する場合は、雇用調整助成金の支給対象となりません。
① 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
② 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検をおこなっている場合を含む)
③ 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(自主的におこなっているものも含む)
(1)「一般事業主」の場合(「対象となる事業主」の2(1))
次の①~③のすべてを満たすこと
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること
② 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
③ 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
(2)厚生労働大臣が指定する事業主の関連事業主(「対象となる事業主」の2の(3))
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減少していること
(3)それ以外の事業主の場合(「対象となる事業主」の2(2)または(4))
次の①および②に該当すること
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減少していること
② 雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと
支給額
雇用調整助成金は、次の1の「対象期間」の期間中におこなわれた休業、教育訓練または当該期間中に開始された出向(ただし3か月以上1年以内の出向に限る)について、2によって算定された額が支給されます。
1 対象期間
(1)「一般事業主」の場合
(上記「対象となる事業主」の2(1))
① 「休業等実施計画届」(下記「受給手続」1(1)参照)の初回提出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間(1年間で100日、3年間で150日を上限日数とする(※2))
② 「出向実施計画届」(下記「受給手続」2(1)参照)の提出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間
(2)「雇用維持等地域事業主」の場合
(上記「対象となる事業主」の2(2))
地域ごとに厚生労働大臣の指定する日から起算して1年間
(3)「大型倒産事業主または大型生産激減事業主の関連事業主」の場合
(上記「対象となる事業主」の2(3)
大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して2年間
(4)「認定港湾運送事業主」の場合
(上記「対象となる事業主」の2(4))
事業主ごとに認定を受けた日から2年間
※2 休業または教育訓練の場合、判定基礎期間ごとの休業または教育訓練の延べ人日数を当該期間に含まれる暦月末日
現在の雇用保険被保険者数で除して計算した日数の累計が上限日数に達した後は支給対象となりません。
2 支給額
(1)休業の場合
休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額(※3、※4)に、下表①の助成率を乗じて得た額(※5)
(2)教育訓練の場合
教育訓練を実施した際に支給対象者に対して支払われた賃金相当額(※3、※4)に、下表①の助成率を乗じて得た額(※5)に、さらに下表②の加算額を加えた額
(3)出向の場合
出向を実施した際の出向元事業主の負担額(※6)に、下表①の助成率を乗じて得た額(※7)
| 助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| ①助成率 | 2/3 | 1/2 |
| ②教育訓練の場合の加算額(支給対象者1人1日あたり) | 1,200円 | |
※3 事業所の前年度の1人1日あたりの平均賃金額に、事業所の「休業手当等支払い率」を乗じて算出します。教育訓練の場合の「休業手当等支払い率」は労働契約か就業規則により特段の定めがない限り、実際に100%とする必要があります。
※4 休業・教育訓練をおこなった判定基礎期間内に、支給対象者が所定外労働等をしていた場合、支給額はその所定外労働等に相当する賃金額を控除した金額となります(残業相殺)。
※5 支給額は1 人1 日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(平成31年3月18日現在で8,260円)を上限額とします(教育訓練の場合の加算額は上限額に含みません)。
※6 出向前の通常賃金の1/2の額が上限額となります。
※7 支給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額に330/365を乗じて得た額が上限額となります。
受給手続
1 休業または教育訓練を実施する場合に雇用調整助成金を受給するためには、次の(1)~(2)の順に手続きをおこないます。
(1)休業等実施計画届の提出
対象期間内の各「支給対象期間」(※8)ごとに、当該支給対象期間の前日までに、当該期間に係る「休業等実施計画書」に必要な書類を添えて管轄の労働局へ提出します。
なお、初回の計画届を提出する場合は、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」を添付した上で、休業または教育訓練を開始する日の2週間前をめどに提出しなければなりません。生産指標および雇用指標の確認等は、この初回分のみについておこなわれます。
(2)支給申請
対象期間内の各「支給対象期間」(※8)ごとに、当該支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請をおこないます。
※8 事業所における賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間を「判定基礎期間」といいますが、事業主は、初回分の計画届の提出時に、「判定基礎期間」の1~3回(1~3か月)分のいずれかを「支給対象期間」の単位として指定することができます。対象期間の初日が判定基礎期間の途中にある場合、対象期間の初日から当該判定基礎期間の末日までを、直後の判定基礎期間に含めることができます。また、対象期間の末日が判定基礎期間の途中にある場合、当該判定基礎期間の初日から対象期間の末日までの期間を、直前の判定基礎期間に含めることができます。
2 出向を実施する場合に雇用調整助成金を受給するためには次の(1)~(2)の順に手続きをする必要があります。
(1)出向実施計画届の提出
出向開始日の2週間前をめどに、必要な書類を添えて、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」、「出向実施計画書」を管轄の労働局へ提出します。
(2)支給申請
出向開始日から起算して最初の6か月間を第1支給対象期、次の6か月間を第2支給対象期とし、各期の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請をおこないます。
私がサポートさせていただきます。

代表:南 大輔
取扱サービス
各種助成金支給申請のサポート
営業時間
10:00~20:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
定休日
日曜・祝日
お電話でのお申込みはこちら